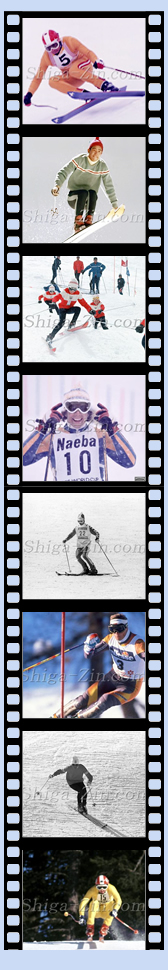【連載21】2回の節目、ルスツ技選の意味は Shiga Zin
※連載21は、連載20からの続きとなります。
 「スキー写真家志賀さんの顔写真を撮るのは緊張します」と話したら笑顔をいただきました |
◆今読んでいただいても、「今の日本のスキーを知る」資料になる
 横浜ランドマークのクリスマスツリー |
 北海道チームの牽引者となった吉田幸一 |
 藤本進以来のスター 佐藤正人 計算されつくした演技は非の打ち所がなかった |
 藤本の秘蔵っ子石井俊一 しなやかな身体の動きは、観客を魅了した |
 石井と共に吉田、出倉らと北海道王国を 築いた細野博。豪胆な滑りは1度頂点を極めた |
 佐藤正人のよき後輩として、山形県の デモ代表選手となった渡部三郎 |
 デモンストレーターの系譜は佐藤正人から 渡部三郎へ、そして次の世代へ |
 元ナショナルチーム出身、佐藤譲は センスある滑りでその潜在能力の高さを示す |
 努力の人、渡辺一樹 |
今にして思えば、前回前々回に掲載した座談会が行われた1987年頃、日本のスキー界は最盛期にあったと言っていい。
1980年代、ヨーロッパスキー界には不況の波が押し寄せていたのだが、日本には逆にすさまじいばかりのスキーブームがあった。
それは、ヨーロッパのスキー関係者が、「日本のスキー」に注目する流れを呼んでいた。
私はその当時、全日本スキー技術選手権大会、デモンストレーター選考会を取材して、スキージャーナル、実日のスキー、山渓のスキーヤーに大量のレポートを寄せている。最近この連載を始めるために、その当時の資料を読みかえしているのだが、その中に今改めて読んで欲しいいくつかのレポートがあった。今読んでいただいても、「今の日本のスキーを知る」資料になるだろうと思い、ここに再録をしてみたい。今回ご紹介するのは、実業の日本社から出ているSKI97の連載の第一回目である。
◆SHIGA ZINの桜吹雪が見えないか? 「SKI97」実業の日本社より
スキー界のお奉行様、志賀仁郎の厳しく研ぎ澄まされた目とペンが、様々な問題の核心を鋭くえぐりだす。
ルスツでの全日本スキー技術選手権、この大会が意味したものは?
そしてこの競技がたどりつこうとしているところとは?
「節目になる大会」という言葉を、何度聞かされただろうか。
16年前の1980年、16年続けられてきた全日本デモンストレーター選考会は、当時大和ルスツと呼ばれていた北海道の小さなスキー場で、第1回全日本基礎スキー選手権大会と、第17回全日本デモンストレーター選考会のふたつの行事に分離された。そして昨シーズン。ルスツリゾートと名称を変えたビックなスキーエリアで、全日本技術選手権大会と全日本デモンストレーター選考会が開催され、さらに、全日本から分離された国際技術選が、新たに設けられる最初の年を迎えていた。
この全日本スキー連盟(SAJ)の大行事が、ふたつに分けられた16年前、そして3つに分離された昨シーズンを、人々は「節目」と呼んでいたのである。
◆大和ルスツから始まった1980年代の技術選が歩んだ道
1980年、大和ルスツでの第1回基礎スキー選手権大会は、1位吉田幸一、2位佐藤正人を筆頭に、それまでほとんどその名を知られなかった新鋭たちが上位を占めた。1970年代、デモンストレーター選考会に4回連続トップをかざり、デモ中のデモと呼ばれたスーパーデモ藤本進が、現役引退後に育て上げた若者たちであった。
藤本厩舎と呼ばれた藤本の弟子たちは、この大和ルスツの大勝利から、約10年、基礎選(のちに技術選と改称)を勝ち抜いた。その10年間は、藤本一門の時代と呼んでいい。デモを目指す俊鋭たちは、こぞって藤本の元へ集まっていた。
藤本の指導は徹底していた。門下生たちは基礎選、技術選に勝つためのノウハウをたたき込まれ、高得点を引き出すすべり、フォームを身につけて雪の舞台に立った。彼らはまさに、雪のサイボーグと言っていい。目線の位置、指先の表情までにも気を配る藤本厩舎の若者たちの出現によって、技術選はスポーツの領域を超えて、様式美を求める古典芸能のような世界に入っていた。正確で美しい、日本独自のスキー技法を完成させていたのである。
基礎選、デモ選のふたつに分けられた行事はどう進行していただろうか。大和ルスツでは、基礎選に続いて行われるはずの第17回デモ選は悪天候のため行われず、基礎選上位者の中から、指導員資格をまだ持っていない細野博、出倉義克、紺野光弘といった若者をを外して、デモの25人が認定されている。分離の意味はまったく感じ取れない結果となった。「基礎選は純粋に技術の優劣を決める選手権大会。デモ選は日本のスキーを表現し、指導者の鑑となる優れたスキー教師を」とした指針は、この年には見えていない。節目は、節目となっていなかったのである。
大和ルスツに見えた節目は、「スキー教師なんかをしていては、基礎選、デモ選の上位は狙えない。これからは、この試合に勝つためのノウハウを身につけた、サイボーグたちの時代だ」という現実であり、そこから生まれたプロの世界であった。
デモと呼ばれる男たちは、日本のスキー界で特異な位置を占める存在となっていた。彼らはインタースキーに参加し、日本のスキー技術や指導理論を世界の人々に披露する。スキー教師のモデルとして日本の技術を演じて見せる。その役割は十分に果たしている。しかしながら、デモとは、日本のスキー教師の模範となる優れたスキー教師でなければならないとした理想像は達成されていない。彼らはデモであっても、スキー教師ではなかった。
その後基礎選は1981年、82年と八方尾根に、83年は岩手県の網張に、84年、85年は青森県の大鰐にと、場所を移して開催され、デモ選は82年、84年と行われている。
この80年代、世界は激動の時代であった。アフガン戦争の激化が示す、地域紛争の多発の時代であり、米ソ二極支配の構造が崩れ、米ソは対立から協調へと政策を転換、長い冷戦の時代が終っている。
日本はその時代、中曽根政権の民活政策によって不況からにわかにバブル経済に向けて一気に走り始めた時代であった。
「父さんゴルフ、僕スキー」それはバブル経済の進行と共に起きた日本の風景であった。そのバブリーな時代背景の中で、大和ルスツ以降の基礎選、デモ選は進行して行った・
藤本厩舎の支配はより強固なものとなり、様式美のスキーは更なる洗練を求めていた。吉田幸一、佐藤正人、細野博、石井俊一。藤本進に育て上げられたサイボーグたちは、この10年間を戦い続けた。
1980年大和ルスツから、1986年八方尾根までの6年間、日本のスキーは、新しい潮流の中にあった。それは「美しいスキー」であった。
1965年、バドガスタインのインタースキーに参加した日本のスキーは、「オーストリアのスキーをオーストリア以上に完璧に表現した」と評価され、1968年、オーストリアがスキーバイブルをさえ呼ばれた古いオーストリア教程を捨てたにもかかわらず、日本のスキー界はその古い教程を信奉する姿勢を変えていない。正確なフォーム、美しいスキー。それは、日本人の感性に合致したスキーであった。
そんな時代背景の中で、デモはこの時代、日本のスキー界のスター集団になっていった。ワールドカップに出場するトップレーサーたちよりも、一般のスキーファンにとって魅力のあるスキーヤーの存在。それがデモとよばれる10数人の男たちであった。
大和ルスツで勝利した藤本厩舎の若者たちは、日本のスキー界のスーパースターとなった。大和ルスツ以来10年間、スターデモとして人気のトップに立った佐藤正人、吉田幸一、細野博、石井俊一、渡部三郎らは、日本のスキーの潮流を生み出す源流にあり、日本のスキー界のファッションリーダーとなった。
しかし、その藤本厩舎の支配が崩れようとする予感は1985年の大鰐に感じられ、1986年に八方尾根に戻った第23回の大会、基礎選ではなく技術選と呼ばれることになった大会では、現実のものとして見えていた。
ワールドカップを転戦してきたレーサー、斉木隆、沢田敦ら日本のアルペン競技会のトップレーサーたちのこの行事への参加が、様式美のスキーに新たに、「速さ・強さ」の刺激を持ち込んだのである。
◆技術選、デモ選分離開催の思想が結実 市場の理論が大頭した八方での6年
1986年から91年までの八方尾根の6年間に、日本のスキーは大きな転流の季節を持つことになった。「スキーのスポーツへの回帰」。それが八方で生まれた潮流であった。
アルペンレース界出身の参入者たちによって上位が占められる時代が訪れていた。渡辺一樹、佐藤譲、沢田敦、斉木隆、金子裕之、我満嘉治らが上位に並び、藤本厩舎の中でその勢力に対抗できたのは、渡部三郎、佐藤正人、出口沖彦らわずか数人だけであった。その小賀坂グループの数人も、もとはアルペン競技選手としての経験をもっていたのである。
速く、強いスキー。それが日本のスキーの新たなテーマとなった。
そしてこの八方尾根で、大和ルスツで提唱された「技術選は誰がスキーがうまいかを決する選手権大会、そしてデモ選はスキー教程の忠実な具現者」とするふたつのイベントの分離の意味がようやく確認されている。1988年の第25回技術選の上位には、1位渡辺一樹、佐藤譲、5位沢田敦、9位斉木隆と、アルペンレーサーが並んでいるが、続いて行われた第21回デモ選では、1位吉田幸一、2位佐藤正人、3位竹村幸則、4位渡部三郎、5位里吉敏章と、レーサーではない男たちの顔が並んでいる。技術選トップの渡辺一樹は13位にとどまった。
1980年、SAJが掲げた技術選、デモ選分離の思想は、8年の歳月を要して、ようやく実現したと言えるだろう。節目はこの1988年、八方尾根で見えてきたのである。
八方尾根に戻って開催された、1986年第23回から1991年第28回の技術選までの6年間は、この行事がもっとも盛り上がった季節であった。どの種目の斜面も大観衆に囲まれた。「この大会はやっぱり八方でなければ」と確認された6年でもあった。大和ルスツ、網張、大鰐の会場の寂しさが思い起こされていた。
そしてその6年は、日本のスキーが、美しく正確な様式美のスキーから、速さ強さを求めるスポーツとしてのスキーへ回帰する潮流を生み出した6年でもあったのである。
また、この6年は技術選のもつ別の側面が見えてきた期間でもある。それはすなわち、技術選の結果がそのままマーケットにつながるという認識の浸透であった。
技術選の勢力地図が、そのまま日本のスキーマーケットの動向を左右する。そしてスキーに関する全ての情報が「技術選」から流れ出ている。それが、日本最大のスキーイベントに成長した技術選の、もうひとつの顔であった。
「日本人のスキー技法」が、ここで演じられたトップスキーヤーたちのすべりから分析され、スキー雑誌、スキービデオといったマスコミによって伝えられる。「佐藤正人のウエーデルン」「渡部三郎のコブのテクニック」「渡辺一樹のパラレルターン」といった技術に関する情報は、日本の若者たちの技術信仰を深めていった。そして、スターたちの使用するマテリアル、さらに着用するウエアについての関心は年を追って高くなり、各メーカーも競って新製品、試作品をここに投入することになった。
技術選は日本のスキーマーケットの動向をうかがう、「新製品発表会・展示会」となったのである。
八方尾根、尾瀬岩鞍、野沢へと移った技術選は、SAJの行事のひとつから、SAJが主催する最大のイベント、そして、日本のスキー界の流れを見透す情報源となっていった。さらに、海外のスキー関係者の視線は、日本だけにある特異な競技会といったものから、世界最大のミラクルマーケットを支配する見本市市場という視点にかわってきたのである。
技術選は今、SAJの行事と言う枠をはるかに超えて、日本のウインタースポーツシーンを演出する、巨大なムーブメントなのである。
◆外国人選手に上位を奪われた技術選 そこに生じた新たな”節目”
1992年、技術選・デモ選は、群馬県の尾瀬岩鞍スキー場に移って開催された。それは、大きな実験であった。「技術選は八方でなければ」の常識に対するSAJのあえての挑戦でもあった。
群馬県の尾瀬岩鞍スキー場。それまでとくに知名度の高くなかったスキー場での開催は、しかし、群馬県連、地元スキー場の周到な準備と、SAJ教育本部の現場役員たちの努力によって、八方尾根から移っての開催への不安を解消している。その尾瀬岩鞍での大会は、1990年から始まった国際化が直実に進行していることを証明した技術選となった。
15名参加した外国人のトップスキーヤーに上位が独占される事態が生じていた。尾瀬岩鞍の2年目には、アメリカ人のマイク・ファーニーが、参加3シーズン目にして遂にトップに立った。渡辺一樹、佐藤譲の「速さと切れ」の時代は、あっ気なく崩れ、技術選は一気に国際化に向かっていた。そしてそれは、94、95年、野沢に映された大会でさらに加速度を増していったのである。
だが、国際化が進行した尾瀬岩鞍、野沢の4年間は、技術選がより高みを目指して再生された期間でもあった。競技種目が見直され、競技の斜面もさらなる難易度を求めて準備されていた。世界のトップスキーヤーの参加による刺激は日本選手たちを目ざめさせ、より高い技術を求めての研鑽の風土を構築した。
技術選。それはまさに、ほんとうにスキーのうまい奴は誰か、本物のうまいスキーとはどんなスキーなのかを見せ、競い合う場になっていたのである。
そして、スキーマーケットのきびしい商戦の最前線としても、完全に成熟した場となっていた。日本のスキー界の情報発信基地としての体制は、八方、尾瀬岩鞍そして野沢で完結していた。
1994年、95年と技術選は野沢で開催された。この野沢で、八方尾根、尾瀬岩鞍で試みられたこの行事のリニューアルが完成したと言っていい。野沢技術選は、30年を越えるこの行事の歴史の中で、もっとも充実した大会と評価されるであろう大会となった。
「誰がいちばんうまいスキーヤーなのか」の技術選は、「うまいスキーとはどんなスキーなのか」「これからのスキー技法とはどんな技法なのか」とその視点を変えていた。より難度の高い斜面でより高い技術と、というSAJ教育本部の要求に、野沢温泉スキークラブは完璧とも言える状況設定と運営で応えたのである。技術選とは、こうあるべきだったのだとの思いを、ほとんど全ての関係者が感じ取っていた。
その野沢で、いいスキーとは何かを見せたのはマーク・ガルシア、ベルント・グレーバーらの外国人であった。マイク・ファーニーに続いて、3年連続外国人のチャンピョンが生まれていた。そして女子の競技では、1990年のフランチェスカ・クラスニッツアー、91年以降のマテア・スヴェトの4連勝と、外国人に上位を占められると言う状況が生まれている。
日本のスキー界にしかない奇妙な競技会、技術選は、野沢で、国際的な認知を得たといえるはずであった。
しかしながら、その野沢では、何かシラケたムードが漂っていたのも事実である。そのシラケムードを生んだのは、言うまでもなく、急速に進んだ国際化の波であった。このままでは、日本のスタースキーヤーたちの影が薄くなり、技術選の人気が下降するのではないか、とする不安、さらに言えば、日本にいない、普及活動に参加することのない外国人ばかりの技術選になってしまっていは、普及振興に役立つとしたSAJの狙いとは違った方向にこの行事は行ってしまうのではないか、との危惧もあった。
日本選手たちの間には、強い危機感が生まれ、日本選手を抱えるオフィシャル・サプライヤーの間にも動揺が起きていた。「このままでは、技術選は出稼ぎ外国人たちのものになってしまう」とするその不安は、野沢に移ってさらに増幅されていった。日本のスキー界は、黒船の来航ほどのショックの中にあった。バブル景気にわいていた日本経済が一気に崩壊したと同じ時期、日本スキー界もまた、バブル崩壊という波をかぶっていたのである。
日本選手たちの味わった危機感は、とうてい世界のトップにはかなわないとする挫折感であり、このままでは俺たちの人気も消えてしまうとする無力感でもあった。
「全日本選手権とうたう日本人の競争なんだから外国人は締め出せ」といった主張が生まれ、「今さら外国人を締め出すわけにも行かないだろうから、外国人はオープン参加として日本人にだけ全日本の順位を与えたら」といった案も浮上していた。まさに技術選が迎えた新たな「節目」の存在が見えていたと言えたろう。
技術選をどうするのかの方向性を探る論議でなければならなかったのである。しかしながら、全日本技術選、国際技術選とふたつのイベントの分離は、日本のスキー人気とマーケットの思惑の中だけで進行していた。
そして昨シーズン。そうした、主に、「日本の技術をどうしていくのか」の視点に立っての議論がほとんどされないままに、技術選は全日本と国際技選とに分離開催されることになった。それは主に日本人選手、日本人選手を抱える企業に間に発生した不満を解消するうえでは、ひとつの解決策ではあった。
しかしながら、八方尾根、尾瀬岩鞍、そして野沢の3会場に起こり、進展した技術選をとりまく状況は、技術選に勝つこと、技術選で目立つことが、巨大なスキーマーケットに決定的に優位をもたらせるとう市場の原理が確立したことであり、同時に、日本のスキーに大きな影響を与える最大の情報発信の基地となっているという事実であった。
◆大成功と言われているルスツでの技術選 しかし、同時に大問題も生じている
16年ぶりにルスツリゾートで開かれた第33回全日本技術選は、SAJ及び北海道スキー連盟の教育本部の人々と地元スキー場の協力によって周到な準備がなされ、好天に恵まれた会場すべての競技がスムーズに運営された。関係者の口からは「よかったよかった」の声ばかりが聞かれ、ルスツ技術選は成功した、とする評価が下されている。
だが、果たしてその評価は当たっているのだろうか。さらに言えば、人々が口にした節目とは何だったのだろうか。それは、この行事がこれから先、どう進展行くかを見定めたうえでなければ、言えない結論である。
私たちは、、日本でいちばんうまいスキーヤーとして、猪俣一之を選び出した第33回技術選になにを見たのか。日本のスキーヤーたちの演じた技法の上に、日本のスキーの新たな可能性を発見できただろうか。答えは暗い。
長年この技術選を見守ってきた私の目には、外国人選手を締め出したことで日本のトップスキーヤーたちの間に、何か和んだ空気が生まれ、緊張感が薄らいでいるように見えた。世界のトップスキーヤーたちと競い合わされ、その尺度で採点された日本人スキーヤーたちが、再び渡辺一樹、佐藤譲、我満嘉治といったベテランスキーヤーを尺度とするレベルに戻って、挑戦者としての上向きな姿勢を失ってしまったと見えたのである。手の届かない高みにある、ベルントやエゴン・ヒールツェガーと同じ土俵での技術選から、ほぼ横並びの実力と見える仲間内の競技会なら、俺もほどほどのところへは行ける。まぁちょっと目立つすべりさえすれば…。日本の若者たちの間に蔓延する横並びの意識が、ルスツの斜面の熱気を失わせていたのである。
挑戦者であったはずの、粟野利信、大盛宏幸、豊野智弘らでさえ、守る側に立っているという状況からは、日本の将来のスキー技法の可能性を見ることは出来ないのである。
採点する審判員の側にも、横並びの思想が入り込んでいる。「俺はこのスキーをこう評価したんだ」という確信的な採点は全く見られず、ここにも、技術選審判法のマニュアル化の進行がうかがえるのであった。
選手、審判の双方に横ならびの思想、マニュアル化の現象が生まれてしまっては、技術選は、新たな技法を発見する場、革新的な技法の実験場とはならないはずである。技術選は15年前に戻って、日本人の好きな様式美の世界、技術選に勝つためのノウハウをたたき込まれたサーボーグの世界に逆戻りしてしまうとさえ思われる。
日本のスキー技法の可能性をさぐる。日本のスキー技法の漂流を見るという視点に立てば、ルスツからは何も見えてこなかったのである。このまま甘いムードの中での技術選は、いつか国際技術選が定着した時、全日本はそれへの挑戦権を得るための国内予選となってしまう危険性がある。
◆世界のスキーまでも視野に入れて技術選をどうするか考えよう
また、このルスツ技術選を、八方尾根、尾瀬岩鞍、野沢の先にどう構想していたのかが、ルスツの会場で感じ取れなかったのはなぜだろうか。それは、八方以外ではダメだ、としていた空気が、尾瀬岩鞍、野沢に次いでルスツでも「とにかくよかったよかった」のムードの中で、どこでやってもいいじゃないかの安堵感を生んだからではないだろうか。
日本人だけの全日本技術選33回をルスツリゾートで行おうとするSAJの決定の裏側では「年と共に拡大し、人気を得た行事を次はどこで開催させるか」の議論のみが先行し、熱心に誘致を働きかけているルスツでやらせてみたらの話ししか聞こえてこなかった。それは、SAJ教育本部の行事とする意識しかなかったということを意味するように思われる。技術選開催には、この行事を日本人のスキーが進歩していく過程を見定める観測点として、どこで、どの斜面で、どの種目をやるのかの視点を持たなければならないはずだ。また、日本のスキーを生み出す源泉地をどこにするのか、日本のスキー界の最大の情報発信の基地をどこに、どう構築するのかの意識を持つ必要があったはずなのだが。
ルスツ技術選に見えたものは、2回の野沢技術選で完成された種目の構成、会場設定、そして運営のノウハウがマニュアル化されて使用されていたということではなかったろうか。そしてこのマニュアルにそって忠実にやれば、どこでやってもうまくいく、との自信がSAJ教育本部の人々の笑顔にうかがえたのである。さらに言えば、その自信は、この先、技術選をどこにするのかの議論を、国体の持ちまわり開催の方式にならった、地方組織の活性化と、スキー場の知名度向上の思惑、そして集客力の向上といった意識での開催地決定の実績を作り上げてしまったと見える。今、SAJ内部では次の第34回をどこで開催するかが検討されている。その会場選びは慎重であって欲しい。
「技術選をどうするのか」。そこには、日本のスキーをどういう方向にもっていくのかという、将来に向けての展望が求められているのだ、という認識に立っての議論が必要なのである。さらに言えば、世界中のスキー関係者の関心を集める行事になっている技術選、国際技術選なのだ、との認識も求められている。世界のスキー界に向けて、新たな潮流を生み出す、という意識もなければならないのである。
ルスツで第33回を終え、さて次はどこで、スキースポーツはどうあったらいいのかの提案として、この先、2つの技術選は開催されなければならないと思うのだが。
連載「技術選〜インタースキーから日本のスキーを語る」 志賀仁郎(Shiga Zin)
連載01 第7回インタースキー初参加と第1回デモンストレーター選考会 [04.09.07]
連載02 アスペンで見た世界のスキーの新しい流れ [04.09.07]
連載03 日本のスキーがもっとも輝いた時代、ガルミッシュ・パルテンキルヘン [04.10.08]
連載04 藤本進の時代〜蔵王での第11回インタースキー開催 [0410.15]
連載05 ガルミッシュから蔵王まで・デモンストレーター選考会の変質 [04.12.05]
連載06 特別編:SAJスキー教程を見る(その1) [04.10.22]
連載07 第12回セストのインタースキー [04.11.14]
連載08 特別編:SAJスキー教程を見る(その2) [04.12.13]
連載09 デモンストレーター選考会から基礎スキー選手権大会へ [04.12.28]
連載10 藤本厩舎そして「様式美」から「速い」スキーへ [05.01.23]
連載11 特別編:スキー教師とは何か [05.01.23]
連載12 特別編:二つの団体 [05.01.30]
連載13 特別編:ヨーロッパスキー事情 [05.01.30]
連載14 小林平康から渡部三郎へ 日本のスキーは速さ切れの世界へ [05.02.28]
連載15 バインシュピールは日本人少年のスキーを基に作られた理論 [05.03.07]
連載16 レース界からの参入 出口沖彦と斉木隆 [05.03.31]
連載17 特別編:ヨーロッパのスキーシーンから消えたスノーボーダー [05.04.16]
連載18 技術選でもっとも厳しい仕事は審判員 [05.07.23]
連載19 いい競争は審判員の視点にかかっている(ジャーナル誌連載その1) [05.08.30]
連載20 審判員が語る技術選の将来とその展望(ジャーナル誌連載その2) [05.09.04]
連載21 2回の節目、ルスツ技術選の意味は [05.11.28]
連載22 特別編:ヨーロッパ・スキーヤーは何処へ消えたのか? [05.12.06]
連載23 90年代のスキー技術(ブルーガイドSKI’91別冊掲載その1) [05.11.28]
連載24 90年代のスキー技術(ブルーガイドSKI’91別冊掲載その2選手編) [05.11.28]
連載25 これほどのスキーヤーを集められる国はあるだろうか [06.07.28]
連載26 特別編:今、どんな危機感があるのか、戻ってくる世代はあるのか [06.09.08]
連載27 壮大な横道から〜技術選のマスコミ報道について [06.10.03]
連載28 私とカメラそして写真との出会い [07.1.3]
連載29 ヨーロッパにまだ冬は来ない 〜 シュテムシュブング [07.02.07]
連載30 私のスキージャーナリストとしての原点 [07.03.14]
連載31 私とヨット 壮大な自慢話 [07.04.27]
連載32 インタースキーの存在意義を問う(ジャーナル誌連載) [07.05.18]
連載33 6連覇の偉業を成し遂げた聖佳ちゃんとの約束 [07.06.15]
連載34 地味な男の勝利 [07.07.08]
連載35 地球温暖化の進行に鈍感な日本人 [07.07.30]
連載36 インタースキーとは何だろう(その1) [07.09.14]
連載37 インタースキーとは何だろう(その2) [07.10.25]
連載38 新しいシーズンを迎えるにあたって [08.01.07]
連載39 特別編:2008ヨーロッパ通信(その1) [08.02.10]
連載40 特別編:2008ヨーロッパ通信(その2) [08.02.10]
連載41 シュテム・ジュブングはいつ消えたのか [08.03.15]
連載42 何故日本のスキー界は変化に気付かなかったか [08.03.15]
連載43 日本の新技法 曲進系はどこに行ったのか [08.05.03]
連載44 世界に並ぶために今何をするべきか [08.05.17]
連載45 日本スキー教程はどうあったらいいのか(その1) [08.06.04]
連載46 日本スキー教程はどうあったらいいのか(その2) [08.06.04]
連載47 日本スキー教程はどうあったらいいのか(その3) [08.06.04]
連載「世界のアルペンレーサー」 志賀仁郎(Shiga Zin)
連載48 猪谷千春 日本が生んだ世界最高のスラロームスペシャリスト [08.10.01]
連載49 トニーザイラー 日本の雪の上に刻んだオリンピック三冠王の軌道 [08.10.01]
連載50 キリーとシュランツ 世界の頂点に並び立った英雄 [08.10.01]
連載51 フランススキーのスラロームにひとり立ち向かったグスタボ・トエニ [09.02.02]
連載52 ベルンハルト・ルッシー、ロランド・コロンバン、スイスDHスペシャリストの誕生[09.02.02]
連載53 フランツ・クラマー、オーストリアスキーの危機を救った新たな英雄[09.02.02]
連載54 スキーワールドカップはいつからどう発想され、どんな歴史を積み上げてきたのか[09.02.02]
連載55 東洋で初めて開催された、サッポロ冬季オリンピック[09.02.02]
※使用した写真の多くは、志賀さんが撮影されたものです。それらの写真が掲載された、株式会社冬樹社(現スキージャーナル株式会社)、スキージャーナル株式会社、毎日新聞社・毎日グラフ、実業之日本社、山と渓谷社・skier、朋文堂・スキー、報知新聞社・報知グラフ別冊SKISKI、朝日新聞社・アサヒグラフ、ベースボールマガジン社等の出版物を撮影させていただきました。