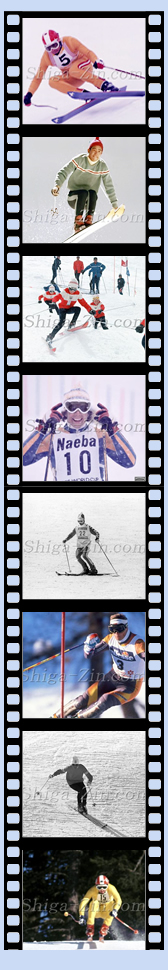【連載54】スキーワールドカップはいつからどう発想され、どんな歴史を積み上げてきたのか Zin
 横浜みなとみらいのクイーンズイースト魚力にて (2007年8月日撮影 上田) |
◆スキーワールドカップはいつからどう発想され、どんな歴史を積み上げてきたのか
私は最近この連載に関して、多くの人々から感想や意見、励ましを聞くことができる様になった。それは、嬉しいことだが、中にはハッと気付かされ、驚かされることがある。そうした質問の中に「志賀さん、ワールドカップと気軽に書いているけど、そもそもワールドカップって何なのですか?」という質問があった。そこで私は、自分で知っている積もりになっているこの巨大なレースを知らない人がかなり沢山いることに気付いた。40年を越えて戦われてきたW・CUPだが、どんな競争で、どう歴史が刻み込まれて来たかについて、私はこの約30年近い年月、説明して来なかった事に恥ずかしい思いを感じている。
W・CUPが創設された当時、それから約10年間ほど私は何度もそのことを書いてきたのだが、もう充分に日本のファン達に伝わっていると思い込んでいるのだということに気が付いたのである。基礎スキーに関する話題を一時お休みにして、この新たな連載をはじめる時、改めてW・CUPの紹介をしておこうと思う。
 SKI WORLD CUPスキーワールドカップのすべて ZIN SHIGA ベースボールマガジン社 |
◆ワールドカップの歴史とルール
雪のナポレオンと呼ばれた名コーチ、オノレ・ボネに率いられたフランススキーチームは、1966年の8月南半球ではじめて開催された世界選手権大会ボルティヨの雪の上で猛威を振るい、オーストリア、スイスらの精鋭を蹴散らした。フランス勢が手中にしたメダルは全メダル18個のうち16個、6つの金メダルを含む。
このポルティヨの大会で、実力世界一は誰かを決めるレースの方式が討議された。そのきっかけを作ったのは、フランスの有名なジャーナリスト、セルジュ・ラングである。ラングの提案は、ほとんどの有名選手が参加するFISのA級レースの中から、いくつかを選び出し、その試合の順位によって、各選手にポイントを与え、そのシーズンの総計によって実力世界一を決めようというものであった。
 |
◆サーキットレースの誕生
FISのマーク・ホドラー会長もこの提案を支持して、このプランの具体化をワールドカップで組織委員会に委嘱した。このプランは、1967年5月ベイルートで開かれたFISの総会で可決され、ワールドカップは、FISの公式のイベントとなった。そしてこのレースに、フランスの飲料水会社エビアンが、クリスタルグラスの美しいトロフィーとメダルを寄贈し、このレースのスポンサーとなった。1968年以降、このシリーズレースはFIS,アルペンスキー ワールドカップ エビアン・トロフィー争奪戦と呼ばれることになった。
COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN F.I.S. Trophee Evian.
このシリーズレースには、男子ではアールベルグ・カンダハーレース、ラバーホーンレース、ハーネンカムレースの3つのクラシックレースを含み、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、北欧、そして日本を転戦するようスケジュールが組まれた、サーキットレースである。
 きびしい実力の世界・ワールドカップ |
◆アルペン競技のありようを変えさせた40年
選手達は、12月の第1週からまったく休みなしの強行スケジュールで、ヨーロッパからアメリカ、カナダと転戦して技を競い世界一の栄光を求めるのである。
このワールドカップの興行的な成功によって、FISのカレンダーは、このレースを中心に組まれることになった。そして一流選手たちの生活は、すべてこのレースのスケジュールにそって組まれることになった。1年間約120日の長い間レースを追ってヨーロッパ、アメリカを転戦するのである。かつて、IOCにアマチュア規定による長期間の休業の禁止といったルールは、アルペン競技の世界には、まったく適合しない現実が生み出されたといっていい。
1967年に始まったこのレースは、すでに40年の歴史を積み上げたわけだが、その40年は、アルペン競技のありようを変えさせた40年となったのである。
ワールドカップの得点は、それぞれのレースの1位に25点、2位20点、以下、15,11,8,6,4,3,2,1、と10位までの選手に与えられる。そして最初の優勝者キリーは3種目にそれぞれ75点ずつを積み上げて、255点の高得点をマークしたのである。
 ロジャー・ロサミニオ |
◆ワールドカップをかざったスターたち
1967年の勝者はキリーだが、この年のキリーの強さからいえば当然すぎる栄光であった。ウェンゲン、キッツビューエル、メジェーブ、セストリエール、フランソワの5つの滑降に連勝の記録は、それから、8年間破られることがなかった。キリーはこのシーズン300点近い高得点を上げていたはずである。2位は、オーストリアの新鋭ハイニー・メスナー、3位は、フランスのギイ・ペリラ、4位ラクロア、5位ムーディと、フランスが圧倒的な強さを見せた。
女子は、ナンシー・グリーンと、マリエル・ゴワシェルの最終のレースまでの大接戦が記憶されるが、その結果は、ジャクソンホールで、2種目に勝ったグリーンのものとなった。
1968年も、キリー、グリーンの王座は変わらず、2人とも、この2年連続の栄誉をあとに引退し、ワールドカップは、新しいスターを生み出すことになったのだが、続く1969年のシーズンでは、アールベルグのライオンと呼ばれ、アールベルグ・カンダハーレースの常勝軍とたとえられたベテラン、カール・シュランツのものとなった。この年シュランツは、クラシック3大レースの滑降をすべて勝って、この種目にマキシマムポイントを上げ、大回転にも70点と、王者らしいレース振りを見せた。このシュランツを追ったのは、ヤングキリーと呼ばれたジャン・ノエル・オージェ、大回転、回転の2種目のみで、123点を上げて、スラロームスペシャリストと呼ばれる地位をつかんだのである。
女子は、カール・シュランツと同じサン・アントンの生まれのゲートルート・ガーブルがクリスタルトロフィーを手中にし、このアルペン競技発祥の地は、歓呼にわき返った。その時、この街のメインストリートには、この村に、世界一のスキーヤーがいる、といった横断幕が誇らしげに下げられていた。
 アラン・ペンツ |
◆スティルビオの天使とうたわれたグスタボ・トエニ
1970年のシーズン、このワールドカップに脅威の新鋭が出現した。 スティルビオの天使とうたわれたグスタボ・トエニである。18歳の美少年は、シーズン開幕の第1戦、バルジゼールの大回転に、リュッセル、ジャン・ノエル・オージェをおさえて優勝、続くヒンデラングのスラローム、リエンツの大回転を連勝、イタリア人を狂喜させた。
1971年に入り、ルールの一部が変更され、選手の出場資格が、男子50ポイント、女子60ポイント以内となった。(ポイントが低いほどレベルの高い選手)その当時、この制限のなかに入り得る力を持つ選手は、男子では各種目50人から70人といったきびしいものであった。当然、日本チームなどの弱小チームはワールドカップレースから締め出されることとなった。グスタボ・トエニは、この年、見事な成長を見せ、回転、大回転の2種目に、パトリック・リュッセル、ジャン・ノエル・オージェの2人のスペシャリストと常にトップを争い、ビステの周辺をわかせたが、この両種目に共に70点の高得点をマーク、滑降にも、アメリカ、シュガーロフのレースに3位に入り、15点を上げて、アンリ・ヂュビラール以下のフランス人3人を突き放したのである。ところで、この時、スラロームの鬼才ジャン・ノエル・オージェの不運によって、ルールは再び改正されることになった。続く1972年のシーズンからは、各種目5レースが採用されることになった。
 ジャン・ノエル・オージェ、ルディ・マット、ロジャー・ロサミニオ |
◆ワールドカップ1975
表彰台の中央に立って大観衆の歓呼に応えるトエニの表情は、あくまでも明るい。再びスキー王者の地位に返り咲くことのできたこのイタリアの英雄は、彼の生涯でもっともはなやかな一瞬に頬を紅潮させていた。
手を高くかかげるトエニのわきで、いつものようにちょっとはにかんだ魅力的な笑顔のステンマルクが、ふっと淋しそうな表情を見せる。わずか数分前まで彼の手につかまれるかも知れなかったクリスタルトロフィーが、一段と高い台に立つ英雄の手に輝いている。
フランス、オーストリア、イタリア3国の選手にしかその栄光のチャンスのめぐってこなかったワールドカップを、北欧に持ち帰るとの期待を、ワールドカップの9年間の歴史の中ではじめて持たせたが、それを追いつづけて、最後の最後、あとわずか数秒というところで取り逃がしてしまったのである。この少年の胸に去来する思いは、どんなものであったろうか。
1位グスタボ・トエニ250点、2位インゲマル・ステンマルク245点、3位フランツ・クラマー240点。台上に立った3人は、誰もが、ワールドカップ史上に不滅の記録として残されるであろう多くの勝利を積み上げたスーパーエースである。ステンマルク、クラマー、そして4位のグロスにしても、この75年シーズンではなく、他のシーズンにこの得点を上げていたら、彼らはクリスタルトロフィーを自分の家に持ち帰ることが出来たのである。
激戦のシーズンといって、これほど大接戦のシーズンは過去にない。
 2位 インゲマル・ステンマルク |
◆ステンマルク 最高のスペシャリスト
ヨーロッパをめぐり、日本、カナダ、アメリカと転戦してなお決着つかず、再びヨーロッパに戻り、イタリアのバルガルデナに、その最後の決着の舞台がしつらえられた。
このイタリアの新興スキー場に集まったジャーナリスト、そして多くの観衆の興味は男子のトップを争う3人にしぼられていた。街でかわされるあいさつは、”誰だと思う”といった言葉となっていた。
男子滑降は、快晴のチャンピノイのコースに、またまたクラマーが勝って、25点をプラス、彼の得点は240点となり、この時点で、トエニ、ステンマルク、クラマーの3人は、全く同点で並んだのである。
最終日、3月25日、新雪の積もったスラロームピステに、2本のコースがセットされた。このパラレルスラロームという種目ははじめてワールドカップに採用された新しい種目、2本並行に作られたコースを、2人の選手が滑り、先にゴールしたほうが勝つという、単純な方式だが、この日までに32位までにランクされた選手によるトーナメント方式という、従来のアルペンレースにない全く新しいレースである。
イタリアは、この32人の中に7人が入ってアルペン強国の力を見せれば、オーストリアも、クラマー、ヒンターゼア、グリスマンを頂点に7人がエントリーされた。しかし、同じ7人でも、その顔ぶれはこの種目では、絶対的にイタリアが優位に立っている。というのは、オーストリアチームでスラロームが強いのは、ハンス・ヒンターゼアただひとり、数字の上では優勝がねらえるクラマーにしても、この種目が最後に残っては、ほとんど勝ち目はない。
このパラレルスラロームは、ただ、トエニとステンマルクの2人のためだけ32人のレーサーが集められたといっていいレースになった。
そして、準決勝から決勝へと、3つのレースを勝ち上がってきた2人の一騎打ちが、大観衆の見守る中でスタートしたのだが、ステンマルクが転倒、そのままレース放棄という、呆気ない幕切れで、世紀の大レースは終わった。
 1位 グスタボ・トエニ |
◆トエニ 新しいルールに大いに助けられたシーズン
トエニは、このレースに勝って、再び4度目の王者の地位に返り咲いたわけだが、このシーズンのレースを振り返ってみると、新しいルールに大いに助けられたシーズンといっていいであろう。
このシーズンは前シーズンのダブルポイントに変わる新しいルールが採用されたが、そのルールがトエニに75点という高得点をプラスさせたのである。
そのルールは、ワールドカップに選ばれたレースの中で、3つのクラッシックレースにコンビネーションの1位から10位にも25点から1点のワールドカップ得点を与えようというもの。
前シーズンのダブルポイントの考え方よりさらに、オールマイティーの選手に有利なルールとなったのである。
トエニは、このコンビネーションを3つとも1位をとって、回転、大回転のみのステンマルク、グロスより優位に立った。
シーズン前、このルールはトエニよりクラマーに有利と見られていたのだが、滑降のクラマーのスラロームより、スラローム・スペシャリスト、トエニの滑降の方が上だったのである。キッツビューエルでのクラマーにわずか100分の1秒差の2位、クラマーの転倒したメジェーブの9位が、トエニにとって、ワールドカップを再び手中にする大きな足がかりとなった。彼の2年前までのポイントを上回る成績を残しているのである。
 3位 フランツ・クラマー |
◆クラマー コロンバンよりも上
2位のステンマルクは、前シーズンの後半、北欧、東欧に移ってからのレースに驚異的な成績を残し、このシーズンが期待された新人だが、その期待をはるかに上回る成績を残した。大回転で115点、回転に110点と共に種目別の第1位。しかもどちらも新記録とあって、この少年のこの2種目の力は史上最高のスペシャリストと呼ぶにふさわしいもの。転倒途中棄権ということがなければ全レース3位以内というレース振りは、従来のスペシャリスト全てに比較して遜色ない成績である。
3位のクラマーは、オーストリアの滑降陣の中にあってもっとも期待された新鋭だったが、順調にその力を伸ばしてトニー・ザイラー、カール・シュランツ、ジャン・クロード・キリー、ベルンハルト・ルッシ、ロランド・コロンバンの4人の史上最強をうたわれた、ダウンヒルレーサーの全てを上回る成績を残した。もし、メジェーブのコースでスキーが外れなかったら、クラマーは9戦全勝で、ワールドカップのウィナーとなっていたはずである。
9レースに8勝、キリーの5連勝の記録を破る6連勝は、まさにクラマーの独走のシーズンであった。しかも、どのコースでもレコードを短縮するといった離れ業で、もしコロンバンが完調で参加していたとしても、この年はクラマーが上だったろうと万人に認められる力を見せた。
久し振りに全コースが使用されたウェンゲンにおける3秒以上の大差の優勝が、クラマーの力の底知れぬ強さを実証しているといえるのである。
※掲載している写真は、「アルペン競技 世界のトップレーサーのテクニッ 志賀仁郎」、「SKI WORLD CUPスキーワールドカップのすべて ZIN SHIGA」(ベースボールマガジン社)に掲載されたものを使用しています。
連載「世界のアルペンレーサー」 志賀仁郎(Shiga Zin)
連載48 猪谷千春 日本が生んだ世界最高のスラロームスペシャリスト [08.10.01]
連載49 トニーザイラー 日本の雪の上に刻んだオリンピック三冠王の軌道 [08.10.01]
連載50 キリーとシュランツ 世界の頂点に並び立った英雄 [08.10.01]
連載51 フランススキーのスラロームにひとり立ち向かったグスタボ・トエニ [09.02.02]
連載52 ベルンハルト・ルッシー、ロランド・コロンバン、スイスDHスペシャリストの誕生[09.02.02]
連載53 フランツ・クラマー、オーストリアスキーの危機を救った新たな英雄[09.02.02]
連載54 スキーワールドカップはいつからどう発想され、どんな歴史を積み上げてきたのか[09.02.02]
連載55 東洋で初めて開催された、サッポロ冬季オリンピック[09.02.02]
連載「技術選〜インタースキーから日本のスキーを語る」 志賀仁郎(Shiga Zin)
連載01 第7回インタースキー初参加と第1回デモンストレーター選考会 [04.09.07]
連載02 アスペンで見た世界のスキーの新しい流れ [04.09.07]
連載03 日本のスキーがもっとも輝いた時代、ガルミッシュ・パルテンキルヘン [04.10.08]
連載04 藤本進の時代〜蔵王での第11回インタースキー開催 [0410.15]
連載05 ガルミッシュから蔵王まで・デモンストレーター選考会の変質 [04.12.05]
連載06 特別編:SAJスキー教程を見る(その1) [04.10.22]
連載07 第12回セストのインタースキー [04.11.14]
連載08 特別編:SAJスキー教程を見る(その2) [04.12.13]
連載09 デモンストレーター選考会から基礎スキー選手権大会へ [04.12.28]
連載10 藤本厩舎そして「様式美」から「速い」スキーへ [05.01.23]
連載11 特別編:スキー教師とは何か [05.01.23]
連載12 特別編:二つの団体 [05.01.30]
連載13 特別編:ヨーロッパスキー事情 [05.01.30]
連載14 小林平康から渡部三郎へ 日本のスキーは速さ切れの世界へ [05.02.28]
連載15 バインシュピールは日本人少年のスキーを基に作られた理論 [05.03.07]
連載16 レース界からの参入 出口沖彦と斉木隆 [05.03.31]
連載17 特別編:ヨーロッパのスキーシーンから消えたスノーボーダー [05.04.16]
連載18 技術選でもっとも厳しい仕事は審判員 [05.07.23]
連載19 いい競争は審判員の視点にかかっている(ジャーナル誌連載その1) [05.08.30]
連載20 審判員が語る技術選の将来とその展望(ジャーナル誌連載その2) [05.09.04]
連載21 2回の節目、ルスツ技術選の意味は [05.11.28]
連載22 特別編:ヨーロッパ・スキーヤーは何処へ消えたのか? [05.12.06]
連載23 90年代のスキー技術(ブルーガイドSKI’91別冊掲載その1) [05.11.28]
連載24 90年代のスキー技術(ブルーガイドSKI’91別冊掲載その2選手編) [05.11.28]
連載25 これほどのスキーヤーを集められる国はあるだろうか [06.07.28]
連載26 特別編:今、どんな危機感があるのか、戻ってくる世代はあるのか [06.09.08]
連載27 壮大な横道から〜技術選のマスコミ報道について [06.10.03]
連載28 私とカメラそして写真との出会い [07.1.3]
連載29 ヨーロッパにまだ冬は来ない 〜 シュテムシュブング [07.02.07]
連載30 私のスキージャーナリストとしての原点 [07.03.14]
連載31 私とヨット 壮大な自慢話 [07.04.27]
連載32 インタースキーの存在意義を問う(ジャーナル誌連載) [07.05.18]
連載33 6連覇の偉業を成し遂げた聖佳ちゃんとの約束 [07.06.15]
連載34 地味な男の勝利 [07.07.08]
連載35 地球温暖化の進行に鈍感な日本人 [07.07.30]
連載36 インタースキーとは何だろう(その1) [07.09.14]
連載37 インタースキーとは何だろう(その2) [07.10.25]
連載38 新しいシーズンを迎えるにあたって [08.01.07]
連載39 特別編:2008ヨーロッパ通信(その1) [08.02.10]
連載40 特別編:2008ヨーロッパ通信(その2) [08.02.10]
連載41 シュテム・ジュブングはいつ消えたのか [08.03.15]
連載42 何故日本のスキー界は変化に気付かなかったか [08.03.15]
連載43 日本の新技法 曲進系はどこに行ったのか [08.05.03]
連載44 世界に並ぶために今何をするべきか [08.05.17]
連載45 日本スキー教程はどうあったらいいのか(その1) [08.06.04]
連載46 日本スキー教程はどうあったらいいのか(その2) [08.06.04]
連載47 日本スキー教程はどうあったらいいのか(その3) [08.06.04]
※使用した写真の多くは、志賀さんが撮影されたものです。それらの写真が掲載された、株式会社冬樹社(現スキージャーナル株式会社)、スキージャーナル株式会社、毎日新聞社・毎日グラフ、実業之日本社、山と渓谷社・skier、朋文堂・スキー、報知新聞社・報知グラフ別冊SKISKI、朝日新聞社・アサヒグラフ、ベースボールマガジン社等の出版物を撮影させていただきました。