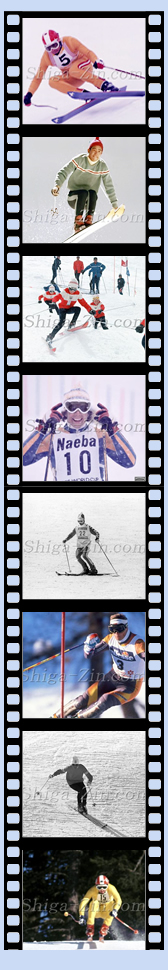【連載27】壮大な横道から〜技術選のマスコミ報道について Shiga Zin
※連載27は、連載25からの続きとなります
 待ち合わせ場所に向かう途中で志賀Zinさんを激写しました |
◆この競技会が大手マスコミに無視されているという実態は理解できない
日本のスキーシーンの中で最大の行事であり、最も権威のあるはずの競技、それは全日本スキー技術選手権大会である。それは通算43年という歴史を超えても、今なほ、日本のスキー界の最大、最高の競技会として存続しているのである。
「全日本スキー技術選手権大会」それが日本における最大、最高のスキー大会である。スキーの世界に生活する全てのスキーヤーにとって常識といえるこの大会は極めて大きな意味を持っている。
ところが、その競技会が、日本のマスメディアでたったの一行も報道されたことがない。何故だろうか、と言うよりも、何故、そんな奇怪なことが40年を超えて進行しているのであろうか。
考えて見なければならない出来事であろう。全日本スキー連盟(SAJ)と大手マスコミの間で何か問題があったのだろうか、また、その両者の間にこの競技会の報道をしないとする約束事でもあるのだろうか。そのどちらも考えにくい。
私は50年を超えてスキースポーツの報道に携わってきた。そして、技術選の43年間の全てを見とどけてきた。その私にも、今、この競技会が大手マスコミに無視されているという実態は理解できないのである。
◆壮大な横道(その1) 1950年代、日本のスキー界はどんな時代だったのか
 山田SAJ理事と志賀Zinさん |
 1959年12月10日 毎日グラフ トニー。ザイラーは1957年突然日本を訪れたが、その後、約4年間、冬の間を日本で過ごした。しかし、SAJは日本のスキーヤーにトニーとの接触を禁じ、トニーと一緒に滑り、トニーと話をしたことのあるのは私を含めて、数人に過ぎない。 |
|
43年前この競技が、どう発想され、どう実現したのか、その時にさかのぼって考えてみたい。1950年代、日本のスキー界はどんな時代だったのか。
ちょっと横道にそれるが、書いておきたい。
大きな戦争が終わり、日本の雪の上に平和が戻って来た時、人々は苦しい生活をさいてスキー場に帰ってきた。その時、スキー技術の教科書は、遠い昔のスキーの神様ハンネス・シュナイダーの記憶、そして戦時中に書かれた軍国教程であった。それは、ハンネス・シュナイダーのアールベルグスキー技法をトレースする、技法であった。
1952年、敗戦国日本ははじめて、オスロオリンピックに何人かの選手が出場を認められた。アルペン競技には北海道、旭鉄の水上久、そして天才少年として知られていた猪谷千春少年の2人であった。
2人が帰国してから、全日本スキー連盟アルペン競技選手強化合宿が、複数回、開催された。当時アルペン競技の一線にいた全ての選手が参加した。
二人の語る世界のスキー、それは極めて刺激的なものであった。
日本のスキー界は、その時に新しい時代を迎えたのである。
1954年、オーレの世界選手権、1958年コルチナ・オリンピック、2つの大きなイベントに、斉藤貢、茂原博太郎、そして猪谷千春、杉山進が参加した。4人が参加した’54年のオーレ、’56年コルチナは、世界のスキーが大きな革命を経験した時代であった。オテマール・シュナイダー、スタイン・エリクセンから、若いトニー・ザイラーの技法に関心が集まり、ヒッコリーの単板のスキーから、ロシニョールの合板のスキー、そしてクナイスルのプラスチックを使ったホワイトスター、ケスレーの合板とプラスチックを同時に使ったスキーと、スキー用具も急速に進歩し、スタイン・エリクセンを王者と呼んだ時代は、トニー・ザイラーの三冠王によって追いやられた。
トニー・ザイラーの人気は、まさに爆発的であった。世界のスポーツ界にスーパースターと呼ばれた人は多い、ゴルフのアーノルド・パーマー、陸上ではグレッグ・ジョーンズ、水泳でジョニー・ワイズミューラー、マーク・スピッツといるけれど、スキーの王者トニー・ザイラーほどのスターを私は知らない。
◆壮大な横道(その2) トニー・ザイラーが突然、日本を訪れた
そのトニーが突然、日本を訪れた。1957年の春であった。ヨーロッパのシーズンを終え、アメリカの3つの大会に招待され、その帰り路、日本廻りのチケットをもらったのである。チケットを贈ったのはアメリカの大富豪、C・V・スターさん 「丁度今頃日本は櫻が満開のはず。それを見物して帰りなさい」という好意ある判断で、当時世界一周便を運航していたパンナムにトニー・ザイラーとヨセフ・リーダーの2人の名手を乗せたのである。
好運はもうひとつ重なった。アメリカから到着する便の搭乗者名簿を点検するのを日課にしていた、旅行エージェントの若い社員賀田四郎君が大のスキーファンであったことだ。彼は日常の業務として行っていた搭乗者名簿の中に、ニュースで聞き慣れていた2人のオーストリア人の名前を見つけたのである。「あの、トニー・ザイラーが日本に来る」の衝撃的なニュースは、直ちにSAJの理事であり、アルペンの強化本部長の、野崎彊さんのもとにとどけられた。
一瞬のうちに「トニー・ザイラーに日本の雪の上で滑ってもらおう」という夢が生まれた。「まだ雪が残り、スキーができるのはどこか」そんな話が飛び交っていた。野崎さんは、日本スキー界の大先輩でありドイツ文学の教授であった、麻生武治さんを引っぱり出して羽田空港に飛び、同時にその前日まで、志賀高原で強化合宿をしていた日本のトップレーサー達に、足止めの指令を出して、上越の水上温泉に集結することを求めた。
羽田で、野崎、麻生の思いがけない出迎えを受けたトニーたちは驚き、困惑していた。「スキーも靴も既に送り返してしまって何も持っていないよ」という彼らに、野崎は一晩できっと全てをそろえるからと約束した。
スキーは、私の持っていたスタイン・エリクセンの2メートル10と、銀座の好日山荘にかざられていた、前の年に来日した、フランスのシャルル・ボゾンの使った、ロシニョール2メーターが、彼らの同意を得て、使われることになった。問題は、2人の履くスキー靴であった。当時、日本のトップレーサーたちの靴を作っていた千住の森戸さんが、何とたった一晩で靴を仕上げたのである。堅い靴を使いニカワで仕上げるという靴は、当時では、10日か20日を要する作業であったはず、森戸さんは、それを一晩で作り上げて水上温泉にとどけた。
◆壮大な横道(その3) 日本のスキー界に真の近代スキーの技法が披露された一日
ゆかたに着替えたトニーとヨセフは日本選手たちと一緒に食卓につき、一緒に温泉の大浴場に入った。全く気取ったところもな、くかざったところもない好青年であった。その場に居合わせた日本人は、たった一晩でトニーのファンとなった。
次の日、春の残雪を塩でかためた石打の斜面で世界一の技が披露された。全日本の特出したレーサー達を集めた合宿という形で急遽、準備された合宿であった。日本のトップレーサー達が、トニーに挑戦を挑んでいた。
日本選手がひとりスタートする。その同じスラロームコースを何秒かおいてトニーがスタートする、懸命に抜かれまいと滑る日本選手をトニーは途中であっさり追いつき、あっという間に抜き去った。わずか30秒から40秒の旗門の中で、世界の頂点と日本のトップとの差は歴然としていた。
ひとり抜け2人抜けて、誰もその挑戦を試みなくなった。石打の残雪の中を自由奔放に滑るトニーとヨセフの2人が居た。
私は一瞬も見逃さない様に2人にカメラを向け続けた。日本のスキー界に真の近代スキーの技法が披露された1日であった。
 1958年12月10日 毎日グラフより この毎日グラフのトニーの滑りの分解は、原稿の中に出てくる、1957年春の突然の来日で、石打で滑った時のもの。 日本におけるトニーの滑りの写真はこの日のものしかない、 |
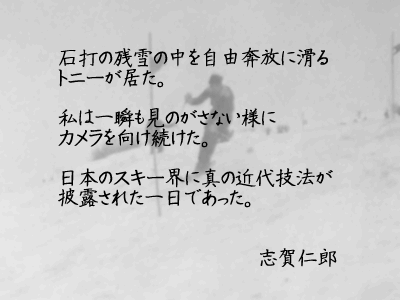 志賀さんが石打でのトニーの滑りを撮った13枚の連続写真 |
◆フランス流からオーストリア流へ
トニーの来日は、日本のスキーに全く新たな流れを生んでいた。その日まで日本のスキー界はフランス流スキー術に流されていた。それまでに来日した、アンリ・オレィエ、シャルル・ボゾン、アンリ・デュビラールといったフランスの名選手たちの滑りに憧れ、「ロッペル」「アタシォン」「ビラージュ」というフランス語があふれていたのである。
「これからはオーストリアだ」 そんな声が上がり、「サンクリストに行って、本物のオーストリアスキーを学んで来よう」、と言う声が大きくなっていた。
かって、スキーの神様、ハンネス・シュナイダーを日本に招んだことのある玉川学園は、オーストリアが新しい教程(1955年)を発表したことを知り、その教程の著者であり、オーストリアスキー教師養成コースの責任者だった、ステファン・クルッケンハウザー教授を日本に呼ぶことになった。
クルッケンハウザー教授は3人の名スキー教師を伴って来日、日本各地で、新しいオーストリアスキーを披露した。その講習会に全日本スキー連盟は、相乗りという形で参加し、オーストリアスキー特別研修会として日本のスキー指導員たちの教育に力を注いだのである。
◆クルッケンハウザー教授と3人の名スキー教師
クルッケンハウザー教授が連れて来た3人のスキー教師、フランツ・フルトナー、バルトル・ノイマイヤーらは、正確で美しく新しいオーストリアスキー技法を演じて見せた。
高い姿勢のフルトナーのスムースなウェーデルン。それは神業に近いものであった。その当時を振返って、クルッケンハウザー教授が語ってくれた。「ウェーデルンという技術が発想されたとき、サンクリストを含めてわずか5,6人が出来るだけの難度の高いものであった。それが次の年には数百人に増え、さらに1年たったら世界中には何万人のスキーヤーが、美しい滑りを見せるようになった。」 と。
日本にも同じ様な現象が起きた。ク教授の研修会の助手を務めた日本の上流スキーヤーの中で、その年、ウェーデルンが出来るようになったのは蔵王の岸英三さん、浦佐の平沢文雄君をはじめわずか数人しかいなかったのである。
日本中にウェーデルン熱が広まった。どこのスキー場のどの斜面にもピョンピョンはねたり、スキーのテールを押しずらしたりの練習風景が見られた。オーストリアスキーはウェーデルンを身につけるために苦行する、スキーの難技法であった。
◆SAJは「世界のスキー事情を探る」視察団をヨーロッパに送ることを決定
ク教授一行が帰国した年、全日本スキー連盟は、理事会で「世界のスキー事情を探る」視察団をヨーロッパに送ることを決定、柴田信一、中沢清、西山実幾、大熊勝郎の4名を選び出した。
4人とも、当時のスキー理論家として注目され、またスキー教師として人気を持っていた名手ばかり。4人は、1962年シーズンインと共にヨーロッパ入りして、視察研究に明けくれた。
「スキーにはオーストリアスキーしかない」4人が到達した結論であった。4人は、ヨーロッパ滞在の後半を全てサン・クリストフで過ごし、自らの技法をオーストリア流に仕立て直していた。
4人が帰国の準備を始めようという頃、クルッケンハウザー教授は、「これからイタリアのモンテボンドーネというスキー場で第6回のインタースキーが開かれる。それを見学して帰ったらどうか、オーストリアチームの客員として面倒を見るよ」と誘った。
4人は教授の好意を受け、そのモンテボンドーネのインタースキーを見学して帰国した。モンテボンドーネで、世界各国の新しい理論、新しい技法に触れても、4人の「スキーはオーストリア」の思いは変わらなかった。
◆壮大な横道(その4) インタースキーに日本も参加しようという夢
そして「次の1965年、オーストリアのバドガスタインで行われる第7回インタースキーに日本も参加しよう」という夢が日本中のスキー関係者のものとなった。
「世界中のスキーをする国が集まって、それぞれの国でどんなスキーをしているのかを、それぞれの国が、その国のトップスキーヤーを滑らせてくらべ合い、理論を戦わせる場だ」
それがインタースキーという行事の目的といった説明がなされ、さて、それでは日本は誰をつれていったらいいのか、誰を「これが日本のスキーです」と言えるスキーヤーなのか。
極めて難しい選択をしなければならないという状況があった。オーストリア、スイス、イタリア、ドイツといった国では、その国のスキー技術、指導理論の頂点にいる帝王の意向によって決まっていた。オーストリアならば、クルッケンハウザー教授が指名するというシステムが完成していた。
「選考会を公開で行って順位の上位から5人を決める」 それが、全日本スキー連盟の総意となった。
「全日本デモンストレーター選考会」1962年春の終わり、残雪の中で行われた選考会はそう名づけられた。デモンストレーターという呼称がはじめて使われたのである。
1位岸英三、2位平沢文雄といった結果が残されたが、その記録は今、全日本のどこにもない。幻の第1回蔵王デモンストレーター選考会と呼ばれる噂だけが今に残されている。
正式の第1回デモンストレーター選考会は、次の年、会場を再び蔵王に選んだ。出場する選手、審査する役員、そして私たちジャーナリストまで一緒の宿に泊まっての選考会であった。居間、食堂、風呂場、全てがデモンストレーターに向けて、スキーをどう滑るかの討論の場になっていた。
1位平川啓紀、2位平沢文雄、上越の小さなスキー場のスキー教師が上位を占めた。平川、平沢に続いて、丸山庄司、北沢宏明、宮沢英雄が上位を占め、バドガスタイン行きの名誉を手に入れた。
その夏、突然トップの平川が体調が優れないため代表を辞退すると伝え、代表は、斉藤城樹が繰り上がって5人となった。
◆バドガスタイン第7回インタースキーは、画期的な論争が戦われた場所
1965年バドガスタイン第7回インタースキーは、スキーの進歩、スキー技術の進展、そしてスキー指導理論の評価、全ての面で画期的な論争が戦われた場所として記憶されるべき会合となった。
既に当時、スキーバイブルと呼ばれる程の信認を得ていたオーストリアスキーメソードに疑問を呈する国があり、またオーストリア国内からも、反発が起きていたのである。
「シュテムをどれ程、習熟しても、パラレルにはならない」とする意見、そして、シュテムとパラレルは全く違ったアプローチからしか習熟できない、といったオーストリアの教程に対する攻撃がエスカレートしていたのである。
そうした攻撃の矢面に立たされた、クルッケンハウザー教授を頂点とするサンクリストフは、55年教程の改造にとりかかっていた。
初めての公式参加となった日本は、世界中の国々から暖かく迎えられた。あんな遠い地球のうら側の小さな国にスキーをする人が居る、という驚き、そしてその国からやって来たスキーヤー達が見事なスキーを演じてみせた、という更なる驚き、地元オーストリアの新聞はこぞって日本のスキーを称えていた。ザルツブルグの新聞には、「遠い東洋の国、日本から来たクルッケンハウザー教授の孫たちは、古いオーストリアのスキーを整然としかも美しく演じて見せた。」と書いている。
高い暖かい評価である。ただ気になるのは日本の5人が演じたのは日本のスキーではなく古いオーストリアのスキーだと見透かされていた事だろう。
インタースキーへの初参加、それは日本のスキーを世界に知ってもらう極めて大きな成果を上げた。このインタースキーを契機として日本は、スキー国として広く知られる様になった。初参加は大成功であった。
日本のスキー界は、このバドガスタインインタースキー以後大きく変わった。
◆デモ選、それは一気に日本のスキー界における最大で最高の選考会
競技のスキーにはオリンピック、世界選手権がある。基礎スキーには、インタースキーという大きな目標があるのだ、といった認識が生まれていたのである。
競技会が1968年グルノーブルオリンピックに動いていた当時、基礎スキー界の人々は1968年アメリカのアスペンで開かれる第8回インタースキーに熱い思いを寄せていた。
デモンストレーター選考会は、バドガスタイン組を選んだ後も続いていた。次はアスペン、それはスキーする若者たちにとって、とてつもない大きな夢であった。デモ選、それは一気に日本のスキー界における最大で最高の選考会になって行った。
2回3回と回を重ねるごとに、この大会のまわりはふくれ上がり、華やかなものとなっていた。選手役員の数が増えるよりも一般の観衆の数が増えていったのである。
◆大手のマスコミが、この競技をどう扱うか迷っていた時代
デモンストレーター選が急速に日本のスキー界に浸透していく中で、一部のスキー関係者の間から批判する声も上がっていた。
「タイムを計らないで順位をつける競争は競技とは呼べない。」「スキー教師とはこういった競技とは無縁のはずだ。」
大手のマスコミが、この競技をどう扱うか迷っていた時代であった。
マスコミに最も強い影響を与えたのは1961年オーストリアに渡り、1964年日本人で初めてオーストリア国家検定スキー教師となって帰国していた杉山進であった。
「ヨーロッパのどこの国にもこうした競技はない。いいスキー教師かどうかは、その教師がいかにお客さんに信頼され、愛されるかによってきまる。日本のこのやり方は間違っている。」
全日本選手権5回優勝の実績を持ってもオリンピックに1回しか出場の機会を与えられなかった杉山にとって、デモンストレーター選考会でインタースキー出場が与えられる方式は、とても許すことの出来ない甘い事象であったろう。
日本の大手マスコミは杉山のその意見を採り入れて、報道するに価しない大会と決め付けてしまったようだ。3回目以降、デモンストレーター選考会を取材するのは1966年に発刊された、スキージャーナルとスキー(実日)、スキーヤー(山渓)、スキー(朋文堂)のスキー専門誌だけとなった。
私は、その頃、大きな新聞社と契約して、デモンストレーター選考会、そしてインタースキーに関する情報を送っていたが、本紙にそのレポートは掲載されることはなく、わずか何頁か、○○グラフ、××グラフといったグラフ週刊誌に採用されるだけであった。
◆『シュテムの消滅』 その日のアスペンは衝撃的な出来事にゆれた
1968年春、第8回インタースキーがアメリカの超有名スキー場アスペンで開かれた。日本からは8人のデモンストレーターを含む30人の代表団がその会議に出席したのである。
この第8回インタースキーは、世界のスキーを根底からゆるがす内容を持ったインタースキーであった。
オーストリアが、世界中からスキーバイブルと呼ばれていた1955年発表のスキー教程を一気に改訂したのである。オーストリアが新しい指導法を雪の上で発表すると決められていた前夜、クルッケンハウザー教授の講演が公会堂で行われた。
教授は開口一番、「1955年に発表した、われわれの指導理論は、長い間に『スキーのバイブル』とまで認められ世界中に普及した。しかし、その指導法をわれわれは今、大きく改正することが必要と考えるようになった。明日、皆さんにお見せするのはその解答である。」と語り、次の日にオーストリアが演じてみせる、新オーストリアメソードを宣伝したのである。次の日快晴のデモンストレーションゲレンデは、世界中の指導者で埋めつくされていた。
5,6歳の幼児を先頭に15〜6人の子供たちの集団演技で始められた、オーストリアのデモンストレーションは、それまでのオーストリアの理論の主要部分を全て捨て去る大胆なものであった。『シュテムの消滅』その日のアスペンは衝撃的な出来事にゆれた。
 1968年毎日グラフ インタースキー特集 「世界のスキーはこれだ」 |
 |
 シュプールは世界を結ぶ |
 ブライトからパラレルへの距離 |
◆アスペン特集は何頁使ってももいいから、克明にやりましょう
「シュテムをどれほど短く、どれほど小さく使っても、シュテムシュブングはパラレルシュブングにはならない」とする攻撃に、鮮やかな反撃であった。
世界のスキー指導理論の先導者は再びオーストリアに戻った。
私は、ただただ、あっけにとらわれてその発表を克明に記録した。
帰国して、持ち帰った膨大なフィルムを現像しながら、私は自分の見てきたものが世界のスキーを動かす極めて重要な意味を持っていると確信していた。帰国してから3週間後にアメリカのオーガニゼーションから分厚い書類が届いた。それは、横浜市の電話帳ほどの厚さの書類であった。世界各国の論文が集められ、さらにひとつひとつの論文に英文の翻訳がつけられた貴重な資料であった。
外国語に堪能な、毎日グラフ編集部の小沢記者は、その論文の全てを読み、「志賀さん、これはすごい事がアスペンで起きたんですね。このアスペン特集は何頁使ってももいいから、克明にやりましょう。」と私をはげましてくれた。
大きな毎日グラフを最大限55頁を使ってレポートが作られた。新聞社が出す週間グラフ雑誌があれ程、大きく頁をさいて報道したという事実を私は知らない。
日本のスキー界に大きな大きな、衝撃波が伝わっていった。「毎日グラフのあの志賀さんのレポートを読まなければ、世界のスキーは判らない」驚異的な売上を記録している。
◆ZINは世界で一番有名な研究者
スキージャーナル社(当時は冬樹社)の滝泰造社長が私に連絡をとって来た。「志賀さんのあの毎日グラフの記事の全文を単行本にしてうちから出させて下さい」という話であった。
その本は、またたく間に出来上がった。「世界のスキー」◆アスペンからの報告書◆と題したB5版の151頁の本であった。
その本は爆発的に売れた。初版はわずか3日で売り切れたと知らされた。私は、売り出しの2日前、見本本3冊をたずさえて、杉山進にさそわれてヨーロッパに渡った。ヨーロッパについた最初の訪問地は、サンクリストフであった。
大きな重い扉を開け、受付のイルミーに来意を告げると、クルッケンハウザー教授はすぐに現れた。何とその時、教授の手には、私の本が握られていたのである。
教授は私たち2人に会うやいなや、手にしていた私の本で、思いっきり杉山の頭をたたいた。「何でお前は、これ程すごい仕事をする男を友達にしているのに、今まで私たちには何も告げていなかったのか」と言い、私に、「お前は素晴らしい仕事をした。私はこの本を手に入れたその時から、この本は私の手の上にある。寝る時だけ、そばにテーブルにあるだけで、私が眼を開いている間は常にこの本は手の中に持っている」と私に語った。
教授は私の本を高く高く評価してくれたのである。教授は、「お前の写真の選び方並べ方でお前が何を語ろうとしたかは判った。」と語っていたが、その後、半年ぐらい経って訪れた時は、私の文章を全てドイツ語に翻訳させて各頁をコピーしそれにその文章をつけて持っていた。そして、「このドイツ語のついたコピーは世界中のスキー研究者の手元にあるぞ、もしかしたら今、ZINは世界で一番有名な研究者だろう」と笑った。
 私の本、『世界のスキー』 この本は、クルッケンハウザー教授に絶賛され、世界中のスキー指導者、研究者により大きな反響と評価を受けて、「世界のスキーにこれ程大きな影響を与えた本はない」と評価された。世界のスキーは大きく流れを変えた。しかし、日本ではSAJから発売禁止の処置がとられ、わずか1000部程度しか販売されていない。「日本のスキー界を混乱におとしめる」というのが大熊勝朗さんの理由だが、そのために日本のスキーは世界から50年おくれることとなった。その後も日本のスキー界は1955年の古いオーストリアスキー教程を順守して今にいたっている。 |
 アスペンの日本チーム |
|
 オーストリア クルッケンハウザー教授 |
 当時の志賀さん |
◆私はただただあきれ、そして悲しんだ
かなり高揚した気分で帰国した私は、全く信じられない話を聞くことになった。スキージャーナルの社長 滝泰造が、私に暗い表情で語った。「あの本が売り出されてからすぐSAJから強硬な要求があり、再版の準備をしていたのに全て捨てた。」と。SAJの幹部は、「あの本は日本のスキー界を混乱させる。アスペンではオーストリアスキーは、一言半句もつけ加えることはなかった。」と言うのである。
私はただただあきれ、そして悲しんだ。アスペンに居た私を含めジャーナリストを加えて36人の日本人は何を見て帰ってきたのだろうか。
私の本が、ク教授にどれ程高い評価を受けたか、そして世界の指導者にどう伝えられているのか、SAJの人々は知り得る立場にあったはずである。しかしながらこの対応は、日本のスキー界の閉鎖性を内外に知らしめることになった。この年以降、サンクリストフは新しい理論、新しい指導法について、全く何も日本に伝えることはなくなった。
日本は、1955年のオーストリアスキー教程を順守する、極めて珍しい国となり世界の新しい指導理論を拒否する鎖国政策をとる国となった。
 毎日グラフ1974年 別冊 スキーへの招待’75 |
 スラローム ダビッド・ズビリング サンモリッツの世界選手権大会に「おいて |
 志賀さんの解説と写真 グスタボ・トニエ(上)丸山隆文(下) |
 アバルマンとヴェーレンテクニックなど ピステからゲレンデへの投影 |
 トップデモの滑りの中に 日本の主張は何か 藤本進(上)、三枝兼径(下) |
 限界に挑むチャンス 丸山隆文 |
◆「世界中のスキー指導者が集まるお祭り」それが蔵王のインタースキーのテーマ
それでもスキー大国日本は、インタースキーの中心に居つづけ、1979年蔵王での第11回インタースキーを開催し、世界のスキー指導者を迎え入れている。
山形県山形市、蔵王温泉の人々は、競技の世界にオリンピック、世界選手権大会があるのと同じように、一般スキーにはインタースキーと言う、世界中が注目する大会がある。と認識していたのである。蔵王は、それまでのどのインタースキーとも違うインタースキーとなった。「世界中のスキー指導者が集まるお祭り」それが蔵王のインタースキーのテーマとなった。友好親善、それが蔵王を極めて特異な空間に仕立て上げた。
どこのホテル、どこの集会場でも陽気に騒ぐスキー教師たちで溢れていた。「こんな馬鹿さわぎをするのがインタースキーではない、次のイタリアでは本来のインタースキーにする」 陽気に浮かれているスキー教師たちに囲まれて、イタリアの団長フィンクはそう語った。
私はインタースキー運動は蔵王のお祭りさわぎと最終日の夜の大花火で終ったと考えている。スキー各国同志の人的交流が進み、情報産業の驚異的な進歩によって、今日サンクリストフで試された技法は、次の日にはシャモニーで、日本の八方尾根で試されるという時代になっているのである。3年に一度集まって技術、指導理論を発表し合うという必要はなくなっているといえるはず。しかしインタースキーは今も続いている。それは、世界中のスキー教師が何年かに一度集まって親交を暖め合う機会があってもいいじゃないかという思いだけなのである。
しかしながら日本人にとってインタースキーは競技の世界にオリンピックがあるなら、一般スキー(基礎スキー)の世界はインタースキーがある。という認識が浸透しているのである。
◆壮大な横道(その5) 北海道のスーパーエースと新潟の若きプリンスの一騎打ちも無視
日本のインタースキーのデモンストレーター選抜の行事はエスカレートしていた。デモンストレーター選考会に出る、デモ選に勝つ、それは「日本一のスキーヤー」と呼ばれる名誉を克ちとるただひとつの道となったのである。
しかし、日本の大手新聞社、テレビ、ラジオのマスコミは、年々巨大化し、年々充実していくこの競技会を無視しつづけた。スキーの世界の人々なら誰でも鮮明に記憶しているはずの北海道のスパーエース藤本進、そしてそれに対抗した新潟浦佐の若きプリンス平川仁彦の一騎打ちのシーンすらも大手マスコミは一行も扱わずに無視しつづけたのである。
◆多くの国が日本のデモ選、技術選を見学に来た
その1970年代から80年代にかけて、ヨーロッパでは、日本がやっている様なデモンストレーター選考会をやるべきではないかという空気が生まれていた。
イタリア、ドイツ(当時は西ドイツ)、スイス、フランス、そしてオーストリアにまでそうした空気が伝わっていたのである。
多くの国が日本のデモ選、技術選を見学に来た。何とそうした人々の中に、その当時、世界一のスキーヤーの名を欲しいままにしていたスイスのピルミン・ツルブリッゲンもいたのである。
八方の総合滑降に前走という形で滑ることを求められたピルミンは後に、「あんなに多くの観衆が見守る斜面を私は経験したことがない。ワールドカップのどのレースのスタートより緊張してスタートした。スタート前、両膝があんなにふるえるのを私は経験したことがない」と語っている。
| 1989年 ピルミン・ツルブリッゲン(スイス) |
※スキー研究シリーズ29「技術選快走録」1996年11月20日発行
スキージャーナル株式会社
◆大手マスコミが無視し続けているということは、異常というより奇怪
しかし、尚、日本の大手マスコミは技術選を無視し続けた。日本で発想され、日本で成長してきた技術選は、年と共に世界に知られる様になり、世界に認められるようになった。
1970年の後半から80年の始めにかけての何年間にイタリア、ドイツ、スイス、フランス、そしてオーストリアでも技術選に似た競技会の開催が話し合われる様になった。
一部のスキー界のボスだけが、インタースキーのデモンストレーターを指名するという方式に対する反発があったはず。日本の方式のほうがより公正であるはずとする常識が浸透していた。
オーストリアが、第一回の技術選を開催した時、その会場オーバーグーグルに日本の杉山進が居たことに私はショックを受けた。彼はオーストリアにおける技術選の提案者のひとりとしてそこに居たのである。日本のデモンストレーター選考会に反対を唱え、激しく批判した、その本人がそこに居るということに、私は激しい怒りを感じていた。節操がないといってこれ程のことは一般には経験することはない。
しかしながら、日本で生まれた技術選が世界に浸透して、今、世界選手権大会にまで発展していることはよろこんでいい。ヨーロッパでは、その世界選手権を大きく報道する様になったのである。何回か前に書いたが、オーストリアの新聞が、ニーナの勝利をたたえて号外まで出しているのである。
ニーナは、私のオーストリアの実家といえる、アンゲラルアルムの長男、アルミンの恋人であり、ホテルのレストランを手伝っている。
アルミンとニーナの2人が写った写真が、そのホテルのあるホッホグーグールのポスターになっているのである。これだけ世界中に普及した競技、そして今、日本のスキー界でこれだけ注目されている競技、それを日本の大手マスコミが無視し続けているということは異常というより奇怪ではなかろうか。
私は、この稿を書き終えてから、大手マスコミのスポーツ担当者に、何故かをうかがってみようと思っている。
 今年のカレンダーの中の1枚。1月、2月でスキーコースに人がたくさんいる写真 ヨーロッパではスキーヤーが戻って来た、良く見ると、その中にはスノーボーダーの姿はない |
 パンフレット見開き 私の泊まるアンゲラルアルムは、この中央のホテル。 3階の角の部屋が私の部屋。写真は3年前、スキー客が全くいなくなった当時のもの |
 今年のカレンダーの中の4月 2人のスキーヤーが向かい合っている 私の泊まるホテルの長男アルミンとその彼女ニーナだ。ニーナは昨年の世界技術選の 優勝者、ワールドチャンピオンである。 |
 私の泊まるアンゲラルアルムのニーナの世界チャンピオンを伝える新聞の号外 |
◆おわび
私のこの原稿を読んでいる人は、ずっと前から 「おやおや、話がいつの間にか、別な方向にずれていっているのではないか」といぶかっているに違いない。書いている当人も、「困ったな、話が広がりすぎて収拾がつかなくなって来たぞ」と思っているのである。
ご勘弁をいただきたい。書き初めた当初から、どの程度の長さに納めるか、どの範囲内に止めるかのマスタープランがあったわけではなく始めた連載だから。こうした混乱は起こり得るべくして起きてしまったと言えば、言い訳には聞いてもらえるかな、などど勝手に思っているのだが。
次回からは、少々整理してから書いてみたい。
以上
連載「技術選〜インタースキーから日本のスキーを語る」 志賀仁郎(Shiga Zin)
連載01 第7回インタースキー初参加と第1回デモンストレーター選考会 [04.09.07]
連載02 アスペンで見た世界のスキーの新しい流れ [04.09.07]
連載03 日本のスキーがもっとも輝いた時代、ガルミッシュ・パルテンキルヘン [04.10.08]
連載04 藤本進の時代〜蔵王での第11回インタースキー開催 [0410.15]
連載05 ガルミッシュから蔵王まで・デモンストレーター選考会の変質 [04.12.05]
連載06 特別編:SAJスキー教程を見る(その1) [04.10.22]
連載07 第12回セストのインタースキー [04.11.14]
連載08 特別編:SAJスキー教程を見る(その2) [04.12.13]
連載09 デモンストレーター選考会から基礎スキー選手権大会へ [04.12.28]
連載10 藤本厩舎そして「様式美」から「速い」スキーへ [05.01.23]
連載11 特別編:スキー教師とは何か [05.01.23]
連載12 特別編:二つの団体 [05.01.30]
連載13 特別編:ヨーロッパスキー事情 [05.01.30]
連載14 小林平康から渡部三郎へ 日本のスキーは速さ切れの世界へ [05.02.28]
連載15 バインシュピールは日本人少年のスキーを基に作られた理論 [05.03.07]
連載16 レース界からの参入 出口沖彦と斉木隆 [05.03.31]
連載17 特別編:ヨーロッパのスキーシーンから消えたスノーボーダー [05.04.16]
連載18 技術選でもっとも厳しい仕事は審判員 [05.07.23]
連載19 いい競争は審判員の視点にかかっている(ジャーナル誌連載その1) [05.08.30]
連載20 審判員が語る技術選の将来とその展望(ジャーナル誌連載その2) [05.09.04]
連載21 2回の節目、ルスツ技術選の意味は [05.11.28]
連載22 特別編:ヨーロッパ・スキーヤーは何処へ消えたのか? [05.12.06]
連載23 90年代のスキー技術(ブルーガイドSKI’91別冊掲載その1) [05.11.28]
連載24 90年代のスキー技術(ブルーガイドSKI’91別冊掲載その2選手編) [05.11.28]
連載25 これほどのスキーヤーを集められる国はあるだろうか [06.07.28]
連載26 特別編:今、どんな危機感があるのか、戻ってくる世代はあるのか [06.09.08]
連載27 壮大な横道から〜技術選のマスコミ報道について [06.10.03]
連載28 私とカメラそして写真との出会い [07.1.3]
連載29 ヨーロッパにまだ冬は来ない 〜 シュテムシュブング [07.02.07]
連載30 私のスキージャーナリストとしての原点 [07.03.14]
連載31 私とヨット 壮大な自慢話 [07.04.27]
連載32 インタースキーの存在意義を問う(ジャーナル誌連載) [07.05.18]
連載33 6連覇の偉業を成し遂げた聖佳ちゃんとの約束 [07.06.15]
連載34 地味な男の勝利 [07.07.08]
連載35 地球温暖化の進行に鈍感な日本人 [07.07.30]
連載36 インタースキーとは何だろう(その1) [07.09.14]
連載37 インタースキーとは何だろう(その2) [07.10.25]
連載38 新しいシーズンを迎えるにあたって [08.01.07]
連載39 特別編:2008ヨーロッパ通信(その1) [08.02.10]
連載40 特別編:2008ヨーロッパ通信(その2) [08.02.10]
連載41 シュテム・ジュブングはいつ消えたのか [08.03.15]
連載42 何故日本のスキー界は変化に気付かなかったか [08.03.15]
連載43 日本の新技法 曲進系はどこに行ったのか [08.05.03]
連載44 世界に並ぶために今何をするべきか [08.05.17]
連載45 日本スキー教程はどうあったらいいのか(その1) [08.06.04]
連載46 日本スキー教程はどうあったらいいのか(その2) [08.06.04]
連載47 日本スキー教程はどうあったらいいのか(その3) [08.06.04]
連載「世界のアルペンレーサー」 志賀仁郎(Shiga Zin)
連載48 猪谷千春 日本が生んだ世界最高のスラロームスペシャリスト [08.10.01]
連載49 トニーザイラー 日本の雪の上に刻んだオリンピック三冠王の軌道 [08.10.01]
連載50 キリーとシュランツ 世界の頂点に並び立った英雄 [08.10.01]
連載51 フランススキーのスラロームにひとり立ち向かったグスタボ・トエニ [09.02.02]
連載52 ベルンハルト・ルッシー、ロランド・コロンバン、スイスDHスペシャリストの誕生[09.02.02]
連載53 フランツ・クラマー、オーストリアスキーの危機を救った新たな英雄[09.02.02]
連載54 スキーワールドカップはいつからどう発想され、どんな歴史を積み上げてきたのか[09.02.02]
連載55 東洋で初めて開催された、サッポロ冬季オリンピック[09.02.02]
※使用した写真の多くは、志賀さんが撮影されたものです。それらの写真が掲載された、株式会社冬樹社(現スキージャーナル株式会社)、スキージャーナル株式会社、毎日新聞社・毎日グラフ、実業之日本社、山と渓谷社・skier、朋文堂・スキー、報知新聞社・報知グラフ別冊SKISKI、朝日新聞社・アサヒグラフ、ベースボールマガジン社等の出版物を撮影させていただきました。